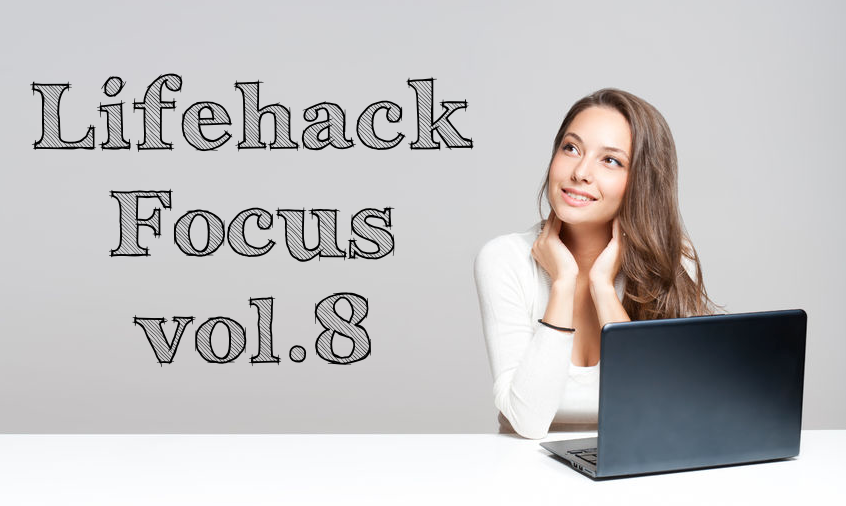歴史の授業で吉田松陰といえば
「松下村塾を開き、明治維新に大きな影響を与えた」
「安政の大獄の犠牲になった」
ぐらいのことしか習わないし、下手をすると授業では人名がさらっと述べられて、後は受験対策に吉田松陰、安政の大獄、松下村塾のキーワードを覚えさせられるぐらいである。野山獄で囚人達に孟子を教える為に記したという「講孟箚記」の名が挙がることはまずない。
確かに、幕府老中の間部詮勝の暗殺を企てるなど思想面に過激なところはあるけど、如何に意義ある人生を送るかについて、実に多くの教えを残してくれている。学生の頃にこういった考えに触れられていれば、その後の人生で何かが変わったかもしれない。

See page for author [Public domain], via Wikimedia Commons
■将来の不安と向き合い、ただ己を磨く
この本を読み進めていくと、齢30にも満たない松陰の元に若かりし頃の長州藩士が集まり、例え未熟なところがあろうとも、日本の未来を切り拓くことを真剣に考えながら、共に学び議論を深める様子がありありと浮かんできた。
恐らくは、彼らとて明治維新は予見できていなかったであろうし、その後長州藩が起こした攘夷行動である下関戦争などからも分かるとおり、当初は列強から日本を如何に守るかが主眼であったのだろう。
松陰は松下村塾に入塾を希望する少年達に「教える、ということはできませんが、ともに勉強しましょう」と言い、同じ目線で語り、同じ目線で議論を交わしたという。
将来の事なんて分からないし、何かを為せる見込みも保証もない。ただ、それでも、まだ何者でも無い自分たちがいつかは大事を成し遂げんと心に誓い、それに相応しい人物になるべく学び、行動し、覚悟を磨き続けた。
なんでもやってみる
できないのではなくて、ただやっていないだけです。まだやったことないことを、「怖い」「面倒くさい」「不安だ」と思う感情は、過去の偏った経験が作り出す、ただの錯覚です。実際にやってみれば、意外とうまくいくことの方が多いのです。
松陰は「行動に繋がらない学問は無意味である」と考えていた。出来るかどうかではなく、まずやってみることを旨としていた。成し遂げられるか二の次であり、自らがやる価値があるのであれば、やるという思考回路だったのだと思う。
先駆者の思考
「なにが得られるか」は後。「自分たちがやる意味」が先です。群れから抜け出したかったら、考え方の順番を思い切って変えてみることです。
松陰は脱藩して奥州を旅したり、死罪を覚悟で外国に渡ろうと浦賀にやってきたペリーの船団の船に乗り込もうとしたり、老中暗殺を企てたりと、よく言えば行動力に溢れ、悪く言えば破天荒な人物である。士籍も家禄も没収され、獄にも二度繋がれ、最後は死罪となった。
逆境に礼を言う
鉄は何度も熱い火の中に入れられて、何度も固い金槌でたたかれて、初めて名剣に仕上がります。人生の送り方もよく似ています。何度も繰り返されるきわめて不都合で、ありがたくない経験の数々が、旅路を美しく輝かせてくれるのです。
ある意味で、逆境に自ら飛び込んでいく生き方であったとも言えるが、それだけ当時の日本に対して危機感を抱き、幕府や世間に対して何とか自らの考えを伝えたいと必死だったということなのだろう。
■若者達が夢の後
吉田松陰は若くしてこの世を去ることになったが、その辞世の句は壮絶だ。
「身はたとひ 武蔵の野辺に朽ちぬとも 留め置かまし 大和魂」
松陰の行動は今の僕らからすれば、何とも命を軽んじているように感じる。恐らくは当時の死生観もあるだろうし、幕府に対して意見すること、或いは自らの考えを広く世に広めるために命を賭したのかもしれない。
しかし、明確に「志を置いていく」と詠んだのだ。
松陰は後事を託せる同志がいたからこそ、自らは命を賭して一撃を打ち込むことができた。自らは何事かを為せなくとも、志を一にする仲間のために活路を拓かんと欲した。それだけ信頼できる能力と志を持つ仲間がいたということに、嫉妬の念を抱かないと言えば嘘になる。
松陰は自らの同志が維新を成し遂げ、明治の元勲となることを知らずにこの世を去った。しかしながら、その目論見は、恐らくは松陰の予想を遥かに凌駕する規模で的中することになる。
明治維新という大事が為されたことを、松陰の先見の明と志、松下村塾の教育の賜で片付けるのは安直に過ぎる。もっと複雑な要因と数え切れないほどの犠牲の上に為された大業であったことは忘れてはならない。
しかしながら、若かった松陰と若かりし頃の明治の元勲たちが、大事を為さんと研鑽と議論を重ね、日夜夢を語らったからこそ、彼らは維新のメインプレイヤーとなり得、維新という大業を成し遂げる事ができたのである。
■最後に
本書は訳者である池田貴将氏の歴史理解がちょっと「?」と思うところはあるけど、記されている言葉自体は大変刺激的であった。
ただし、Amazonレビューでは、この本に書かれている超訳は、現代語訳は勿論、意訳の枠すらも遥かに飛び越えて原型を為していないという意見が散見された。
だからといって、本書からうけた刺激の価値は些かも毀損されるものではないが、松陰が実の所どういった言葉を用いて、何を伝えようとしていたかは知っておきたいと感じたことは間違いない。次は原典にあたり、その真意に直に触れてみたいと思う。